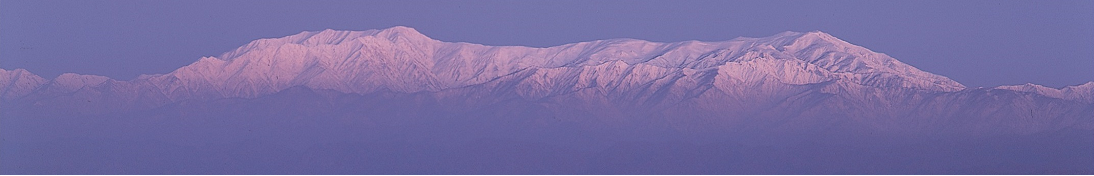人づくりの指針に関する取組のご紹介
本文
人づくりの指針推進事業のご紹介
瓜生岩子の水あめ作り
明治のころ、砂糖は高級品だったので、それぞれの家で炊いたもち米にもやしを混ぜ、発酵させて水あめを作っていました。
岩子は、貧しい子ども達のためにアメを作ってあげたいと思い、高価なもち米より値段の安いサツマイモでアメを作ることに成功しました。
岩子はこの水あめ作りを広め、戦争でけがをして入院している兵隊にもお見舞いとして贈り、喜ばれました。
取組紹介
熱塩小学校と加納小学校の5年生が、岩子が広めた「水あめ作り」を原材料の栽培から一連の作業を体験することで、奉仕の精神を学びました。
5月 サツマイモの苗植え
秋の水あめ作りの材料になる、サツマイモの苗を植えます。
6月 大麦の刈り取り・乾燥
水あめ作りには大麦も使用します。前年度の秋に今の6年生が種を蒔いた大麦を刈り取り、稲架掛けして乾燥させます。
9月 サツマイモ収穫、大麦の脱穀・ごみ取り
今年の夏は暑かったのでサツマイモの育ちが早く、9月に収穫しました。
収穫後は乾燥した大麦を脱穀し、ごみを取り除く作業を行いました。
10月 大麦の芽出しと乾燥・製粉
麦芽を作るため、大麦の芽出し作業を行います。
芽が1cm位に伸びたら乾燥させ、根を取り除いて製粉すれば麦芽の出来上がりです。
11月 大麦の種蒔き
次年度の水あめ作りに向けて大麦の種を蒔きます。
11月 水あめ作り
熱塩加納公民館の佐藤館長に教わります。
今回は、子どもたちが学校田で育てた無農薬栽培のもち米を使った水あめ作りを体験しました。
原料となるもち米をおかゆ状に炊き、麦芽を入れて糖化したものを布袋に入れ、しぼります。
しぼり汁を火にかけて煮詰めます。
水あめの硬さになったら、瓶に詰めて完成です!
もち米で作った水あめと、サツマイモで作った水あめを食べ比べしました。
どちらも甘くて美味しいという声が多く、
「みたらし団子みたいな味がする」「リンゴのような味がする」など、友達同士で感想を言い合っていました。
また、水あめ作りには手間と時間がかかることを知り、「やっぱり瓜生岩子さんはすごい」と、
先人の偉大さを改めて感じることができたようです。