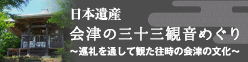日本遺産「会津の三十三観音めぐり」について
1 日本遺産とは
文化庁が、地域の歴史的魅力や特色を通じての文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産(Japan Heritage)」として認定し、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の様々な文化財群を総合的に活用する取組を支援する制度です。
会津の三十三観音めぐり|日本遺産ポータルサイト (bunka.go.jp)<外部リンク>
2 「会津の三十三観音めぐり」とは
東北で最も早く仏教文化が花開いた「仏都会津」。その中でも「三十三観音めぐり」は、古来のおおらかな信仰の姿を今に残し、広く会津の人々に親しまれています。
会津での三十三観音めぐりの起源は寛政20年(1643)、保科正之公の入封以降と伝えられています。
当時、領民のあいだでは伊勢参りや西国三十三観音巡りなどが盛んで、多額の費用が領外に流れていくのを案じた正之公が高僧らと計り、会津にも三十三所を定めたといわれています。
おもに農村部の女性が、田畑の仕事が一段落した7月頃に、白装束に笠をかぶり、講仲間とともに「御詠歌」を唱えながら三十三観音札所を巡礼して回ったそうです。
このストーリーや文化が日本遺産として平成28年4月に認定され、令和4年7月に継続認定されています。
3 日本遺産「会津の三十三観音めぐり」の構成文化財について
日本遺産「会津の三十三観音めぐり」は、国宝を蔵する寺院から山中に佇むひなびた石仏までいたるところにその姿をとどめた様々な文化財で構成されています。
喜多方市内には9つの札所と3つの神社仏閣の計12箇所文化財が「会津の三十三観音めぐり」の構成文化財となっています。
⑴ 喜多方市内の札所(9箇所)
第1番札所 大木観音

いつの頃か判明しませんが、大木村に大木左馬亮という人がいて、常安長者と呼ばれていました。
この観音堂にはその常安長者の物であったとされる十一面観音を安置しています。
天正17年(1589)に伊達勢の兵火にかかり焼失しましたが、上杉氏の時代の慶長3~6年(1598~1601)の間に再建されたと伝えられています。
第2番札所 松野観音

もとの本尊は千光寺の仏像であったとされています。
元禄7年(1694)の火災で像を焼失してしまったため、その後、観音堂の荒廃するのを危惧した星某という者が新たに像を作りました。
その際に焼失した像の灰をその像の中に納めたと伝えられています。
第3番札所 綾金観音

元弘元年(1331)葦名盛宗が建立し、十一面観音像を安置したとされます。
この頃は20を超える僧房があり、隆盛を極めていましたが、天正年間(1573~1593)に兵火にかかり、寛文年間(1661~1672)に石伝という僧が再興したと伝えられています。
第4番札所 高吉観音

文亀年間(1501~1504)に盛尊という僧が中興し、その後、慶意という僧が住み会津若松市大町の一桂院の末寺となったと伝えられています。
元和7年(1621)に火災で像を焼失したため、現在安置されている十一面観音はその後新たにつくられた像です。
第5番札所 熱塩観音

境内にある観音堂は、禅宗様建築の様式が取り入れられ、波状文、龍、鷲、白蓮などの動植物文の浮彫彫刻が施されています。
記録によれば、越後の間瀬大工による天明8年(1788)の上棟であるとされます。
千手観音を安置しており、その像胎内に源翁が所持していた観音小像が納められていると伝えられています。
第6番札所 勝観音・勝福寺(国重文)
国の重要文化財に指定されている勝福寺の境内にある観音堂です。
享禄2年(1529)に前身の観音堂が焼失し、永禄元年(1558)に蘆名盛興によって再建されたと伝えられています。
内部中央には、本尊である観音菩薩を祀ってある内陣があり、内陣のまわりには参拝者が拝む場所である外陣があります。
会津地方には、禅宗様の手法を交えた中世の三間堂が数多く残されていますが、この堂は和様の要素が多く、縦長にした内陣など独特の平面を持っており、中世末期の仏堂として優れたものです。
第7番札所 熊倉観音

天正年間(1573~1593)に兵火にかかり焼失しましたが、安政5年(1858)に再建されたと伝えられています。
堂内には行基作とも慈覚作ともいわれる千手観音を安置しています。
第8番札所 竹屋観音・木造如意輪観音坐像(県重文)

中には県指定文化財に指定されている「木造如意輪観音坐像」が安置されています。
鎌倉時代の仏工師運慶の作と伝わっています。
天正元年(1573)に快元という僧が越後より来て、堂を建立しました。その後、正徳年中(1711~1715)に再建されました。
4間四方で、四方に高欄縁を設けています。世間では、「子安観音」と呼ばれています。
第9番札所 遠田観音

伝承では、旧観音堂は、7間四方の観音堂であり、柱には金を使用し、屋根は檜皮葺とした壮麗な建物であったといいます。
堂内には千手観音を安置しています。
⑵ 市内の構成文化財(3箇所)
中善寺 木造薬師如来坐像(国重文)

平安時代後期の作であり、当時の都である京都方面の仏像様式・定朝様(じょうちょうよう)で造られていることから、中央から会津に運ばれてきたものと考えられています。
願成寺 木造阿弥陀如来及両脇侍坐像(国重文)

古くから会津大仏と呼ばれ、地域の人々の信仰を集めてきました。
光背にある千体化仏は、かつて周辺の村から戦地に出征した人々がお守りとして携えていったと伝えられ、信仰の厚さを知ることができます。
新宮熊野神社文珠堂 木造文珠菩薩騎獅像(国重文)
 今も会津に残る仏像の一つです。
今も会津に残る仏像の一つです。
新宮熊野神社の文珠堂本尊であり、知恵・学問の仏様として地域の人々の信仰を集めてきました。
文珠堂は、会津熊野と称されていた新宮熊野神社境内にあり、磐梯(いわはし)神社を習合していた慧日寺をはじめ、古来より根付いていた神仏習合の信仰、熊野信仰を伝える遺品として貴重です。
4「会津の三十三観音めぐり」情報について
地域の観光および産業の発展並びに地域振興に寄与することを目的として、会津17市町村他関係団体で構成される極上の会津プロジェクト協議会が「会津の三十三観音めぐり」の主体となり、文化財所在地域の活性化を図ることを目的とし、様々な事業を展開しています。
文化庁の日本遺産に選ばれた全国の自治体などが集まる「日本遺産サミット」(仮称)が、2024(令和6)年秋に福島県会津地域で開催されることが決まりました。
今後は、極上の会津プロジェクト協議会を中心として、会津の三十三観音めぐりに関する講演会などを開催し、サミット開催の機運を高める計画となっています。
日本遺産「会津の三十三観音めぐり~巡礼を通して観た往時の会津の文化~」 (aizu33.jp)<外部リンク>
【会津の広域観光はこちら】極上の会津 | あったんです。まだ、極上の日本が・・・ (gokujo-aizu.com)<外部リンク>
5 パンフレット
 |
会津ねがいたび<外部リンク> 会津の三十三観音めぐりのリーフレットです。 |
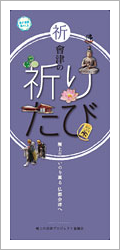 |
會津の祈りたび<外部リンク> 仏都会津の寺社の紹介とその魅力が満載のパンフレットです。 |
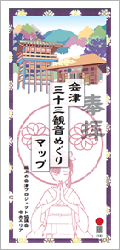 |
会津三十三観音めぐりMAP<外部リンク> 会津三十三観音の紹介と地図が載っているパンフレットです。 |
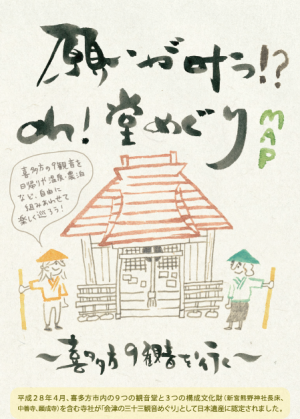 |
喜多方の9札所の紹介と地図が載っているパンフレットです。 |